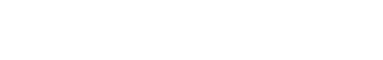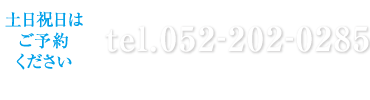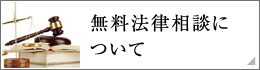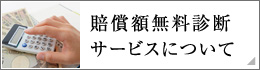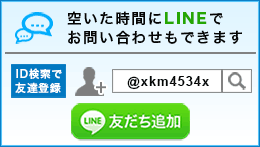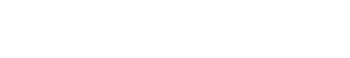Author Archive
【コラム】高齢者運転の死亡事故の割合が増加
警察庁によると,令和4年に自動車やバイクで75歳以上の運転者が起こした死亡事故は,前年に比べ33件増の379件で,死亡事故全体に占める割合が過去最高の16.7%となりました。
1947~49年生まれの「団塊の世代」が75歳になり始め,75歳以上の免許人口が増えた影響があると考えられています。
事故の原因は,ハンドル操作の誤りやブレーキとアクセルの踏み間違いなどの操作ミスが30.1%と多くなっています。事故の類型別では,電柱や標識などへの衝突が最も多く,人が横断中,道路外にはみ出すケースが続いています。
このように,高齢者の交通事故の割合が増えている中,もし,交通事故の被害に遭った際に,加害者が高齢者でかつ認知症だった場合,賠償はどうなるのでしょうか。
加害者が認知症であっても,自賠責保険や任意保険に加入していれば,認知症でない方と同じように,自賠責保険や任意保険から保険金を受け取ることができます。
ただし,認知症の加害者が無保険の場合,認知症の程度により責任能力がないと判断されれば,民法上の賠償責任は負いません。その場合は,自動車損害賠償保障法の範囲で,自動車の所有者が本人であれば本人が,所有者が家族であれば運行供用者として家族が賠償責任を負うことになります。
また,認知症の程度によっては,事故状況の確認が難しく,事故の目撃者がいない場合は,示談による解決が難しくなることもあります。適正な過失割合で事故の解決をするには,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析し,正確な事故態様を明らかにできる,交通事故に強い弁護士に相談することが大切です。
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。
また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
なお,治療の結果,後遺障害が残り,その後事故とは別の理由で亡くなったとしても,死亡の事実は考慮せずに,事故後生存している場合と同様に後遺障害逸失利益は請求できます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,高齢者の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:消極損害 死亡逸失利益
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害 死亡による逸失利益
(1)算定方法
死亡による逸失利益とは,生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のことで,以下の計算式で算定します。
<死亡逸失利益の計算式>
逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数によるライプニッツ係数
ア 基礎収入
逸失利益算定の基礎となる収入は,原則として事故前の現実収入ですが,将来,現実収入額以上の収入を得られる立証があれば,その金額を基礎収入とします。
なお,現実収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても,将来,平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば,賃金センサスの平均賃金を基礎収入とすることができます。
家事従事者の方は,死亡した年の賃金センサスの女子全年齢平均賃金(令和2年の統計で381万9200円)で算定します。
イ 生活費控除率
利益が失われると同時に,もし生きていれば支出するはずだった生活費も支払わなくてよくなっているため,死亡逸失利益を算定するには,将来支払うはずだった生活費を控除します。
被害者に被扶養者がいる場合は年収の35%,被扶養者がいない場合は年収の50%です。女性(主婦,独身,幼児等含む)は,30%です。
ウ 労働能力喪失期間
就労可能年数は,原則として67歳までの期間です。
ライプニッツ係数は,就労可能年数に応じて決まっています。
(2)計算例
※令和2年4月1日以降に発生した事故を想定し,利率は年3%とします。
① 有職者または就労可能者
年齢30歳の主婦の死亡逸失利益の例
381万9200円×(1-0.3)×22.1672=592万62679円
② 18歳未満の未就労者
3歳男子の死亡逸失利益の例
545万9500円×(1-0.5)×16.3686=4468万2185円
※ライプニッツ係数は,67年-3年=64年のライプニッツ係数28.4065から,18年-3年=15年のライプニッツ係数11.9379を控除したものです。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
特に死亡逸失利益は,賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で請求することが大切になります。
保険会社から提示される金額は上記算定方法の金額を大きく下回りますので,適正な死亡逸失利益での解決実績が豊富な,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:愛知県内令和4年交通事故の特徴
警察庁によると,令和4年中の全国の交通事故死者数は2610人となり,前年より26人減少しています。
https://www.npa.go.jp/news/release/2023/20230104001jiko.html
愛知県内の死者数は137人で,昨年より20人増加しています。全国ワーストを4年連続回避していますが,今なお多くの尊い命が交通事故で失われ,多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいらっしゃいます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/kakuteisuu202212.pdf
死者数を当事者別でみると,歩行者が大幅に増えています。
また,自転車の死者20人全員がヘルメット非着用となっており,ヘルメットを着用しないと死亡につながりやすいことが分かります。道路交通法の一部改正により,令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。愛知県では既に2021年10月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっていますので,ご自身や大切な人の命を守るため,自転車乗車時のヘルメット着用を忘れないようにしましょう。
死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は64人となり,死者数全体の半数を占めています。令和4年は,若者(16歳~24歳),一般(25歳~64歳)の死者数が増加しています。
歩行者が被害に遭う交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,逸失利益は賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
高齢者の場合は,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
未就労者(学生,生徒,幼児)の場合は,労働能力喪失期間は原則18歳からとなりますが,大学卒業を前提とする場合は,大学卒業時となります。基礎収入は,若年労働者(事故時概ね30歳未満)として,全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則となっています。
それ以外の方についても,給与所得者なのか,事業所得者なのか,会社役員なのか,家事従事者なのか,失業者なのか,その方によって算定方法が異なりますので,適正な逸失利益を受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,全年齢の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい
愛知県警察によると,令和3年12月22日現在,交通事故による死者数は134人となっており,昨年より20人多くなっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou221222.pdf
愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。
また,強烈な寒波により日本海側では大雪となっている地域があります。年末年始にかけても引き続き大雪の予報が出ていますので,帰省やレジャーなどで車を運転される方は,最新の情報を確認した上で,より安全を心がけて運転してください。
普段あまり雪が降らない地域に住んでいる場合,冬用のタイヤを用意していないことも多いですが,ノーマルタイヤで雪道を走行する行為自体が交通違反となります。
また,大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があるときには「チェーン規制」が発令されますが,「チェーン規制」が発令された場合は,スタッドレスタイヤをつけていたとしても、その上からチェーンを装着しないと走行できません。
雪道であるにもかかわらず冬用のタイヤやチェーンを装着していない場合は,事故発生時,過失割合が加算される場合がありますので,注意が必要です。
では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】12月は業務中,通勤時の死亡重傷事故が年間最多
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,12月は交通死亡事故が多発しています。12月中の交通死亡事故の特徴としては,①歩行者事故として,【年齢】高齢者が6割以上,【時間帯】朝及び夕方から深夜にかけて多発です。②自転車事故として,【年齢】高齢者が約9割,【事故類型】出合い頭が約6割,【時間帯】9時台から13時台が約6割となっています。
また,業務中,通勤時の死亡重傷事故が年間最多となっています。年末は業務多忙となり心身の疲れなどが運転に影響を及ぼすことが予想されますので,体調管理に努めるとともに,時間にゆとりを持ち,速度を控え,安全行動を心掛けることが大切です。
(https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/20221019point.pdf)
業務中・通勤時に交通事故の被害に遭った場合,労災保険から保険給付を受けることができます。業務時間中の事故は業務災害,通勤退勤の途中の事故は通勤災害となります。 労災保険で受けることができる給付は,①療養(補償)給付,②休業(補償)給付,③障害(補償)給付,④傷病年金,⑤介護(補償)給付,⑥遺族(補償)給付,⑦葬祭料があります。
労災保険を使用するメリットとしては,費目間の流用を禁止するルールがあるため,積極損害,消極損害,慰謝料で各費目分類し,各費目の過失相殺後の残額は,いずれも当該費目間に関してのみ既払金及び損益相殺で補填されます。
(例)
過失割合が加害者:被害者=70:30,治療費100万円,慰謝料1000万円,労災から療養給付100万円受給している場合
治療費は,過失相殺すると100万円×70%=70万円となり,損益相殺すると70万円-100万円=-30万円となり,保険会社に請求できる治療費は0円となります。
慰謝料は,労災保険の支給対象外なので差し引かれる給付はなく,保険会社に請求できる慰謝料は過失相殺した1000万円×70%=700万円となります。
治療費が30万円過払いとなっていますが,費目間の流用が禁止されているため,他の費目から控除されることはなく,保険会社に請求できる賠償額は,0万円+700万円=700万円となります。
仮に労災保険を使用せず,保険会社の一括対応で自由診療による治療をしていた場合は,過払いとなった治療費が他の費目から控除されるため,-30万円+700万円=670万円となります。
以上のとおり,労災保険を使用するメリットは多くありますが,損害賠償額の計算方法など複雑な部分もあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,労災保険を使用した交通事故の解決実績が豊富にありますので,労災保険を使用する交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:愛知県内の交通事故死者数が100人に達する
愛知県警察によると,愛知県内の今年の交通事故死者数が100人に達し,令和4年10月27日時点では109人となっています。100人に達したのは昨年(11月18日)より39日早く,愛知県警察では交通ルールの順守を呼び掛けています。
また,亡くなった109人のうち65歳以上の高齢者が48人と最多となっていますが,25~64歳も42人と多くなっています。当事者別では歩行者が,類型別では横断中がもっとも多くなっています。
冬に向けて日没時間が更に早くなることから,自動車はヘッドライトを早めに点灯し,歩行者は反射材の着用をするなど,一人一人が交通事故を防ぐための行動を心がける必要があります。
(https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou221027.pdf)
歩行者が被害に遭う交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。
死亡事故の場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
ただし,67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については,原則として,平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
また,交差点内や交差点付近で歩行者が横断中に事故に遭う場合,歩行者が横断歩道を横断しているかどうかで過失割合が変わってきます。
横断歩道外を横断している場合でも,横断歩道の付近であれば横断歩道通過後なのか横断歩道の手前なのか,それ以外の場所なのかなど,事故態様に応じて過失割合が変わってきますので,ドライブレコーダー映像や事故の現場図を分析し,正確な事故態様を明らかにしたうえで,適正な過失割合で解決することも非常に大切となります。
死亡事故は賠償額が高額となるため,過失割合がたとえ1割の違いであっても,賠償額が大きく変わってきますので,専門的知識と豊富な解決実績のある交通事故に強い弁護士に相談することが重要になります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,高齢者の死亡事故,過失割合について解決実績が豊富にありますので,高齢者の死亡事故,過失割合でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:高齢者交通安全週間の実施
愛知県では,交通事故死者数の半数以上を占める高齢者の交通事故を防止するため,高齢者交通安全週間を,令和4年9月14日から20日まで実施しています。
高齢者交通安全週間では,「高齢者交通事故0(ゼロ)への三箇条」として,高齢運転者及び歩行者に対して,以下の3点を呼び掛けています。
1.「安全運転サポート車(サポカーS)の活用」
2.「運転免許証の自主返納制度の活用」
3.「反射材の着用の促進」
(www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/20200916kourei.html)
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。
また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,高齢者の交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。